「夏休みメディアリテラシー体験講座」(主催:青少年育成尾道市民会議)2日間の初日として、尾道で『ピッケのつくるえほん』ワークショップを行ってきました。会場は、急な坂道を縫うように上った先にある、おのみち生涯学習センター、廃校を活用した市民に開かれた場です。
参加者は、6歳から大人まで14名。福山大学の飯田豊さん、 杉本達應さんとご一緒なので心強く、新しい方法を試してみました。PCでなく初めてiPadを使い、できあがったばかりの2つのiOSアプリを使いました。
まず、持ってきてもらった「ぼくの/わたしのとっておき」を写真におさめ、吹き出しと音声でひとことを足し自己紹介代わりのカードを作成。全員分を前の画面に投影、発表することから始めました。兄弟姉妹やクラスメイトをバラし、属性が異なるどおしのペアーにして座席替え。そこから、いつもの絵本づくりに入りました。
アプリは、新しくつくったiPad版の「ピッケのつくるえほん」を使用し、AirPrintで展開図を出力、まず紙の絵本をつくります。
音声録音も、そのまま同アプリ内で。絵本に書いた文章の通り読むだけでなく、セリフを追加している組が多くありました。例えば「おじいちゃんにあいにいく」では、絵本の文章は「ぶじおじいちゃんのところにつきました」で終わっていますが、音声付では、裏表紙(おじいちゃん=亀のまんねんさん)に、「おじいちゃんひさしぶり」と2人で声そろえて入れています。2人とも、それぞれのおじいちゃんに、この絵本をプレゼントするそうです。他にも「二人の誕生日」では、最後のシーンに拍手が入っています。発表会は、iPadの画面をビデオカメラ経由でプロジェクタに投影、全員で鑑賞しました。(iPad2であれば、直接プロジェクタに繋げることができます)
途中おやつタイムをはさんだとはいえ、4時間ちかくの長丁場。どこまでできるかなと思いましたが、全7組とも、音声録音まで楽しみながらやり遂げました。
今回は「2時間以内で」などの時間制約がなかったので、かなり盛り込んでみました。反省は、導入の「とっておき」を後半の絵本づくりに上手く繋げられなかったこと。同じ場に集って一緒に絵本づくりをすることで新しい友だちができるといいな という裏目的もあったのですが、そこも充分ではなかったと思います。とはいえ、組になった相手とは、もし街で会うことあれば「こんにちは」と言えるでしょうか。
福山大学の学生さんたちが、準備~当日~記録とサポートしてくださいました。感謝です。
>> 子どもたちの「ぼくの/わたしのとっておき」(画像のみ)は こちら
>> 子どもたちの音声付き絵本作品は こちら(YouTube)
>> 杉本達應さんによるレポートページ(東京大学 水越研 media exprimo)は こちら

福岡の夏の恒例「おいでよ!絵本ミュージアム2011」が、今年も福岡アジア美術館で開催されています。
今年の展示は偕成社さんです。(展示については ブログにも書きました)
会期中の 7/31、8/1に 『ピッケのつくるえほん』ワークショップが行われました。
初日は、いつものようにプリントして紙の絵本を作成、プロジェクターで発表会。
お話に凝って文字入れが間に合わなかったにもかかわらず、楽しい物語をしっかりした声で語ってくれた6歳男の子、立派でした。弟にプレゼントする絵本をつくった5歳のお兄ちゃん、カラフルで楽しいお話できました。
2日目は、急遽、音声録音もしてみることに。追加の録音アプリを入れて、入力はPC内蔵マイクを使用。
2時間で盛りだくさんすぎるかも… と心配しましたが、どの子も発表会を楽しみに、がんばってくれました。
全員お話を完成、録音まで完了。発表会では皆、顔が輝いていました。
骨折で入院中の高校生のお兄ちゃんに贈る絵本をつくった5年生の男の子も。
にぎやかな発表会を終え「どうだった?」と聞くと、「すごく楽しかった!」「他のおともだちのお話が聞けて面白かった!」と元気いっぱい口々に答えてくれました。
いちばん楽しかったのは私かもしれません。
>> 1日目の子どもたちの作品は こちら
>> 2日目の子どもたちの音声付き作品は こちら(YouTube)

福岡の2つの会場でワークショップをしてきました。
主催はいずれも、NPO法人子ども文化コミュニティ。これまでも何度かお世話になってきた、任せて安心のプロフェッショナル集団です。皆さん家庭へ戻ればママでもあります。
1日目は、子どもたち対象。幼児は親子で、小学生はひとりもしくは子ども同士のグループ制作。
兄弟姉妹はバラして別グループにする、6年生は未就学児と組ませるなど、事前によく考えてグループ分けされていました。最初はギクシャクしたりもめていたグループも、子どもなりのやり方で、最後は作品にまとめ、仲良く一緒に発表。子どもは柔らかく賢いですね。

2日目は、オープンしたばかりの博多阪急に会場を移して、ママのための講座です。
7階の子ども服フロアに、「子育てコミュニティルーム」という白木の素敵なスペースがあります。
昨日の子どもさんの様子にご自身もつくってみたくなり、友人を誘って参加してくださった方もありました。嬉しいです。小さなお子さんを膝に乗せ、あるいは隣に敷いたマットで寝ている赤ちゃんの気配を感じながら、皆さん、夢中で絵本を作られていました。
博多は、街も人も、まぶしいほどに活気があふれていましたよ。
>> 子どもたちの作品は こちら
>> ママたちの作品は こちら

好評につき3月21日に急遽追加が決まったのですが、震災でいったん延期、子どもの日開催となりました。
今回も講師は、CANVASの熊井さんです。前回同様に、親子で、家族で、できあがったお話に音声を録音します。中には、2部仕立てのお話も。ストーリーでぐいぐい引っ張るお話やアイディアが楽しいお話など、今回も個性あふれる物語がいっぱいです。

>> 主催者によるレポートページは こちら
>> 主催者による作品ギャラリーページは こちら(全54作品を見られます)
「キッズクリエイティブ研究所」は、NPO法人CANVASが開催するこどものためのワークショッププログラムです。東大、慶應大、早稲田大などを会場に行われています。そのプログラムの1つとして「ピッケのつくるえほん」ワークショップが行われました。
私はソフトとカリキュラムを提供し、あとは、熊井さんをはじめとするCANVASの皆さんにお任せ。今回はじめて、新しくつくった音声を録音できるソフトを使ってもらいました。できあがったおはなしに、声を付けます。お父さんやお母さんと一緒に。なかには、おじいちゃん、おばあちゃん、妹さんまで参加して一家総出演でつくるご家族もあったそうです。
子どもたちのつくるおはなしには、ありがとう、いいよ、うれしい という素直な言葉があふれています。
届いた約60作のムービーを見ていると、光景が目に浮かぶようでした。

プログにも書きました。
>> 主催者によるレポートページは こちら
>> 主催者による作品ギャラリーページは こちら(全62作品を見られます)
ワークショップ知財研究会の第5回シンポジウム『ワークショップの事業化を考える』で登壇しました。
会場は、夏にデジタルはらっぱをしたのと同じ、3331 Arts Chiyoda です。
私自身、ワークショップの事業化ができているわけではないのにいいのだろうか…と思ったのですが、ワークショップも含めて、開発したピッケの事業化についてあれこれ試みている様をお話させていただくことで、何かしら皆さんのヒントになるやもしれず、ジタバタやってるそのままを、お話させていただきました。
トップバッターは、ケミカルエンターテイナーのなおやマン&しま:アイさん。シンポジウムとは思えないショーアップされた講演(?というか「エンターテインメントショー」)で、観客を魅了。ワークショップでちゃんと生計をたてている数少ない実践者です。
次は私。普通にパワーポイント。子どもたちの作品や記録ムービーに助けられて。
最初の15分は、自己紹介と「ピッケのおうち」「ピッケのつくるえほん」の紹介。後半30分で、ワークショップでの活用と事業化について話しました。
前半で、ソフトの開発者として心がけていることとして、以下を挙げました。
・活動全体として設計し、支援ツールとして埋め込む
・使いやすくわかりやすく
・子どもの生来の力を信じてソフトを設計する
「ひなたの匂いのするソフトであること」
後半では、次のような内容を話しました。
ワークショップを行うことの、開発・運営者である私にとっての目的
・フィードバックを得る・活動全体として伝える・広報
活動を継続するために
・次開発ソフトは、事業化しよう。
・信用をつけたほうがいい → キッズデザイン賞グッドデザイン賞。法人化。
・商標をおさえる。
「ピッケのつくるえほん」提供先別種類と主な導入・活用例
・パーソナル版/学校版/ミュージアム版/病院版/Facebookアプリ
ピッケの事業化の柱をどうするか
学校やワークショップという、教師やファシリテータがいる場が望ましい。
当面は、学校版を柱にしていく。
事業化することも、ソフトの開発と似ていて、進みたい方向があり、自分のあらゆるリソースを総動員し、たくさんの人に助けてもらい進めている。
事業を軌道に乗せ、ソフトの開発を続け、おはなしづくりの活動をひろめていきたい。
したいことは、子どもを幸せにすること。
・上質の楽しいや嬉しいを体験できる場と機会をつくること。
・子どもたちの心の中に安全基地(コミュニケーションの基盤)を育てること。
3番目ラストバッターは、ビジュアルプログラミング言語「ビスケット」の原田康徳さん。
コンピューターは粘土である。ものをつくり表現することは、大きく2つに分類できる。クレヨンで絵を描いたり粘土で何かを作るのは「直接表現」。オーケストラのために楽譜を書いたり建築物のために設計図を書くのは「間接表現」。「間接表現」には設計が必要。設計してものをつくる楽しさと面白さを伝えたくて、ビスケットを開発し研究室の外へ出て子どもたちとビスケットをされています。
大月ヒロ子さんを座長にパネルディスカッション、続いて茶話会と、盛りだくさんな1日を満喫しました。
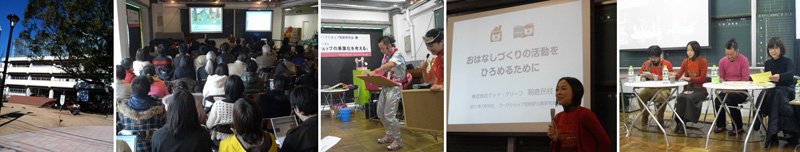
>> ワークショップ知財研のレポートページは こちら
>> 記録映像はこちら
発表スライド:おはなしづくりの活動をひろげるために
今年はじめてのワークショップが広島で開催されました。
主催は、NPO子どもコミュニティネットひろしまさん。メディア表現や演劇表現などを通して子どもたちの表現力を育て、多彩な人が集う新しい地域のコミュニティづくりに丁寧に取り組まれています。スタッフの中に若い方がいらっしゃると思ったら、2人ともスタッフの娘さん。大活躍してくださいました。迎える側も実にアットホームな雰囲気です。
皆さん、親子でご参加くださいました。
パソコンははじめてという子どもたちが半分以上でしたが、まずクリックとドラッグを練習、文字入力はお父さんお母さんに手伝ってもらい、がんばりました。
できあがった絵本をプレゼントする相手は、お父さんお母さん、弟や妹が多かったです。姉妹で参加してくれた2人は、お互いにプレゼントしあいっこ。
3歳~6歳とかなりの低年齢だったので、前へ出ての発表は難しいかもと思いましたが、なんと全員が、お父さんお母さんに伴われてであっても、前へ出てきて発表できました。おそらく、スタートから1時間経った場がほどけ、なごやかな雰囲気になっていたからではと思われます。マイクを使わなかったことも良かったのかもしれません。
部屋のコーナーに、敷物を敷いてオモチャを置いた託児スペースが設けてありました。参加者に同伴した小さな子どもが遊ぶスペースです。預かる人数が多い時には別室に設けることもあるそうです。
全国各地に、地域に根ざした活動を地道に続ける方々がいらっしゃることを知り、とても励まされる思いです。
ブログにも書きました。
>> 開催概要pdfは こちら
